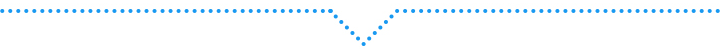- ホーム
- ドラキッズ『まなびドア』
- 小学生の「作文力」に欠かせない「論理的思...
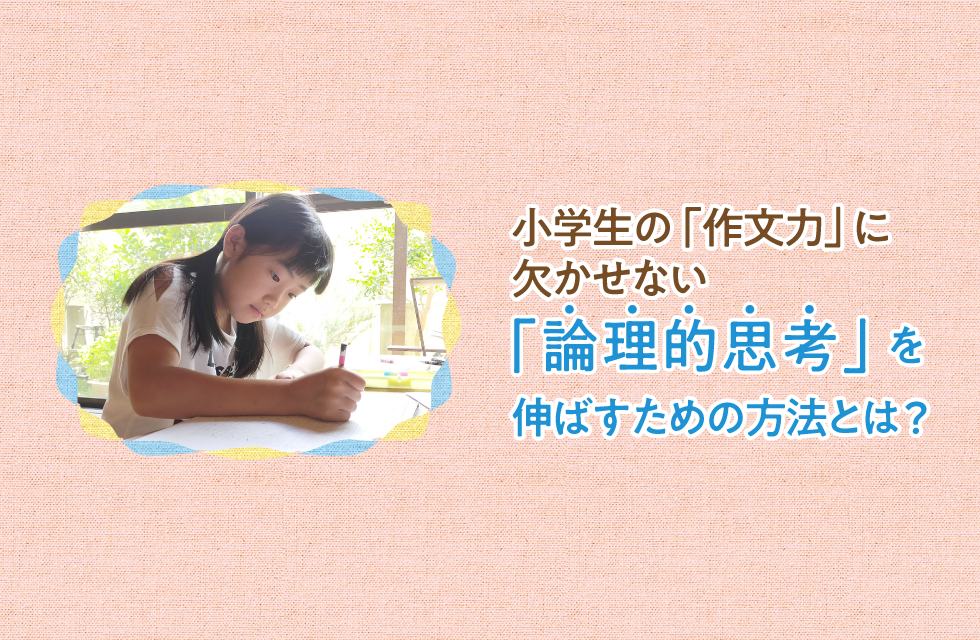
2021年09月13日
小学生になると作文を書く機会が増えますが、「作文ってどう書けばいいの?」と思っているお子さまは、案外多いと思います。
宿題の作文に時間がかかっているお子さまの様子を見たり、お子さまからアドバイスを求められた際に作文の書き方を適切に教えられなかったり、という経験を持つ保護者の方もいらっしゃるでしょう。
そこで、この記事では作文に必要な「論理的思考」についての解説を踏まえて、お子さまの「作文力」アップのポイントを紹介していきます。同時に、「論理的思考」の育み方や『ドラキッズ』小学生コースでの取り組みを伝えます。作文に限らず、年齢が上がるにつれて文章を書く機会はますます増えていきますから、低学年のうちに苦手意識を取りのぞいておけると良いですね。
作文は、特定の人に宛てて書く手紙やメールとは違って、不特定多数が読むことを想定して書くもの。誰が読んでも理解できるように書かなくてはいけません。そのため、自分が知っている言葉を的確に使い、自分の考えや知識などを整理する「論理的思考」が必要だと考えられています。
また、作文に苦手意識を持つ子どもの中には、「何を書いたらいいかわからない」と悩んでいることも少なくありません。このような場合、自分が伝えたいことを見出す力「着眼力」や自分なりの考えを生み出す力「発想力」を磨く必要があります。あるいは、自分なりの考えや発想を持っていたとしても、それを作文で的確に伝えられないと感じている可能性もあります。それならば、「語彙力」や「表現力」を養う必要があるでしょう。
これらの力は、「論理的思考」を土台にして育まれるものと考えられています。「論理的思考」が育まれると、「着眼力」「語彙力」「表現力」「発想力」も自然と高まっていきます。つまり、「論理的思考」と「作文力」の向上は、つながっていると言えるでしょう。
そうは聞いても、「ついこの前、ようやく字を書けるようになったばかりの子どもが、自分の考えや知っていることを整理して、しかも文章を組み立てていくのは難しいのでは...」と感じる保護者の方もいらっしゃるでしょう。
この章では、作文の書き方のコツを紹介するとともに、どの段階でどのような力が必要なのか解説していきます。
「何を書けばいいのかわからない」状態にならないようにするには、伝えたいことを見つけられる「着眼力」が求められます。
小学校低学年の場合、感情に着眼して書くことをおすすめします。
例えば、「遠足について書きましょう」と言われたら、遠足の際に感じた気持ちを思い出して書くのが良いですよ。実際に体験した感情は書きやすいですし、読んでいる人にも伝わりやすくなります。
次に、書くための材料を集めて、それが作文の作成に必要なものかどうか見極めていきます。この作業では、自分で考えて、整理する「論理的思考」が必要になります。
最初は集め方がわからないお子さまもいると思います。 遠足での楽しかったことを書くのなら、保護者の方が「なにが楽しかった?」「なぜ楽しかったの?」などと質問をして、その時感じた気持ちを細かく振り返っていきましょう。自分の感情だけではなく、その時見たことや聞いた音、周囲の人の表情など印象に残っていることを集めてみるのも良いですよ。材料が集まったら、今度は整理をします。「この材料は書きたいことと関係あるかな?」などと聞いて、お子さまが判断できるように導いてあげましょう。慣れてきたら、「友だちの笑顔は、楽しかったことにつながるから材料になる」と自分で考えて整理できるようになっていきます。
材料集めと整理の次は、書いていく順番を考えます。自分で考えて整理する力「論理的思考」があれば、この作業もスムーズに進められるようになります。
作文の苦手なお子さまに多いパターンとして、「時系列」の構成(朝、昼、夕方の順など起こったことを順番で書いていく)でしか書けない、ということがあります。作文の内容によっては、その構成が適切なこともありますが、作文は「時系列」以外で書いていくこともあると伝えましょう。お子さま自身がさまざまな構成で書くことを知っていると、作文への苦手意識や戸惑いも少なくなるのではないでしょうか。
小学校の低学年なら、「はじめ」「まんなか」「おわり」の3つに分けて、何を書くのかを考えていきましょう。
例えば、「はじめ」の部分では、この作文で書く遠足について紹介します。「まんなか」で遠足での楽しかったことを詳しく説明し、「おわり」でそれついて感じたことを書きます。
自分なりの考えを生み出す「発想力」があると、「おわり」の部分で自分の考えや感情をまとめやすくなります。
さらに、この方法で文章の構成を考えるようになっていくと、高学年、さらには中学・高校・大学での作文や小論文、あるいは大人になってからの文書作成にも活用できることでしょう。
「論理的思考」を活かして作文を書く際には、的確に伝える「語彙力」「表現力」が必要です。「楽しかった」「おもしろかったです」など同じような言葉や言い回しを繰り返している文章では、単調な作文になってしまいます。
その時の感情を伝えきれないとお子さま自身が歯がゆく感じることもあるかもしれません。「楽しい」という気持ちも「うきうき」「わくわく」「声がはずむ」「ときめく」などさまざまな表現がありますよね。そのような言葉の中から最適な言葉を選んだり、伝え方に工夫を凝らしたりすることで、文章にメリハリが生まれ、読んでいる人に伝わりやすくなります。
小学校時代は、親子やお友だちとの会話で使う日常的な言葉に加え、プレゼンテーションや作文作成の際に必要とされる論理的な言葉の使い方を育む時期です。この時期に「論理的思考」を高めれば、作文はもちろんすべての教科の学力向上につながるとも言われています。
「作文を書くために必要な論理的な言葉の使い方や「論理的思考」の育成には、特別なトレーニングや高度なテクニックが要るのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。家庭内で日常的に育むことができるので紹介していきますね。
作文への取り組みが増える小2・3でスタートしても良いですが、小1の段階から「論理的思考」を意識しておくのもおすすめですよ。
親子でたくさん会話をしましょう。会話ではさまざまな言葉を使って、語彙を増やすことを意識してくださいね。
会話の中で、常に「なぜ?」「どう思う?」とお子さまに問いかけるのも良いですよ。お子さま自身が理由や感情を説明できるように質問してくださいね。
言葉のキャッチボールをして、会話を展開していく「論理トーク」もおすすめです。
会話をすることで、たくさんの言葉を知りますし、それらの言葉を使って自分の考えを伝える力を養っていきます。
家庭内では親子間の会話が中心になるため、言葉や表現のバリエーションに限度が出てしまいますよね。たくさんの言葉や知識に出会うことで、作文力に必要な「論理的思考」を高めさせたいと考えるなら、『ドラキッズ』への参加を検討材料のひとつにしてみませんか。
『ドラキッズ』は、小学校低学年こそ、日本語の理解を深める時期だと考え、日本語を論理的に学ぶことに取り組んでいます。「論理的思考」向上には、目・口・耳の3つの感覚を同時に使うことが大切なので、授業では音読を意識的に行うほか、身近な言葉の種類分けなどで、言葉の整理、言葉のつながりなどを段階的に学んでいきます。
言葉や文の成り立ちへの理解を深めることで、文章を書くことや、長い文章や複雑な文章を読むことに苦手意識を持たないようにしています。また、辞書を引くことを習慣づけ、語彙を増やす指導を行っています。読解と文章を書くことに特化した「読解・作文トレーニング」の授業も行い、国語力全般を高めています。
多くの子どもたちを指導している講師が、一人ひとりに適切な言葉を投げかけることで、楽しみながら自然に「論理的思考力」を高めます。