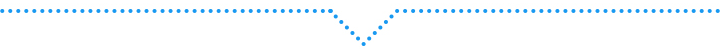- ホーム
- ドラキッズ『まなびドア』
- 国語だけじゃない!「読解力」は他教科でも...
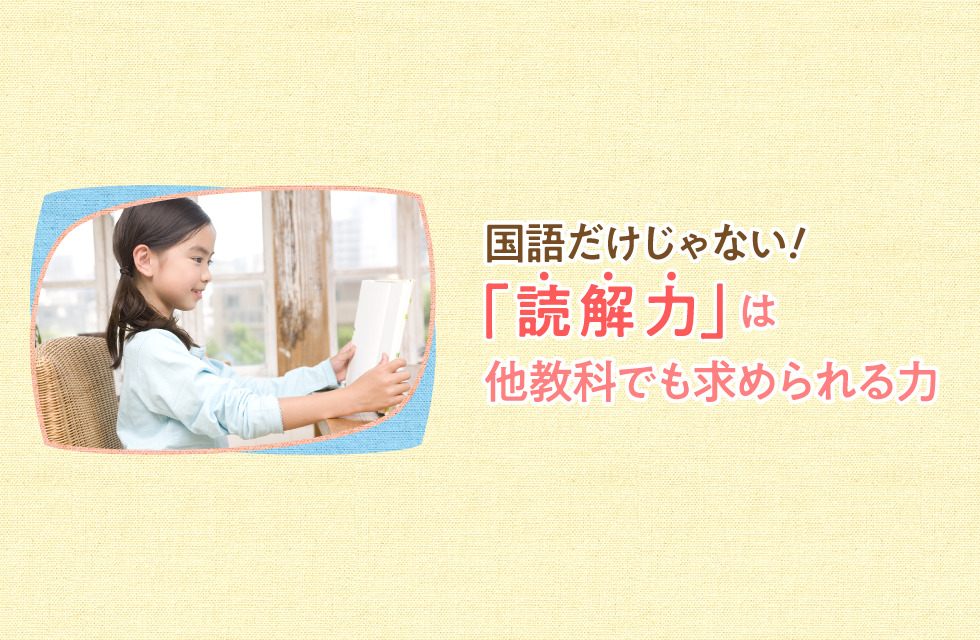
2021年09月03日
お子さまの国語のテストの結果や、算数の文章題が苦手な様子を見て、お子さまの「読解力」に不安を感じたことはありませんか?
小学生の子どもを育てていると、雑誌やニュースなどで「読解力」が大事だと聞いたり、読んだりしたことがあると思いますが、どう大事なのか、何をすれば養われるのか、わからないですよね。
今回の記事では「読解力」の大切さを解説します。また、日常的に行える「読解力」アップの方法や「読解力」養成のための取り組みを紹介していきます。
「読解力」は国語だけでなく、あらゆる教科に共通して役立つ力ですので、記事を参考に「読解力」を高めていけると良いですね。
そもそも、「読解力」とは何なのでしょうか?まず、「読解力」について確認しましょう。
「読解力」と聞くと、読書が好き、国語の読解問題が得意であることと思っている人も多いと思います。でも、「読解力」は、文章を読む力だけを示しているのではありません。「読解力」とは、文章を読んだ上で理解したり、考えたりする力のことを指します。
では、どうして小学生から、「読解力」が大切なのでしょう?それは、小学校での学習では、教科書に書いてある文章を読んで理解していくからです。そのため、国語だけではなく、算数や生活科などすべての教科を学んでいくための基礎として「読解力」が大切だとされているんですね。
また、「読解力」は社会生活のさまざまな場面で求められる力と結びついていると考えられています。たとえば、「読解力」が高ければ、
・自分の考えを深める思考力
・適切な行動を行える社会性
・他者との交流をスムーズに行えるコミュニケーション力
・ものごとを正しく把握できる判断力
が備わると考えられています。
一方、「読解力」が低い場合、
・ものごとを正しく判断できず、間違った行動を取る
・他者との会話がかみ合わないなど、コミュニケーションを上手に取ることができない
・自分の考えや感情を表現できない
ということになってしまいます。
このような点から「読解力」は、勉強に向き合う学生時代だけではなく、一生において役に立つものだと考えられています。
OECD(経済協力開発機構)が実施した国際学習到達度調査によると、日本の学生の読解力は2000年には8位でした。しかし、2018年実施の調査では過去最低の15位という結果に。分析結果から、文章から情報を探し出す力や文章を読んで考える力、矛盾を見つけて対処する力、また自分の考えについて根拠を示して記述する力が低いことが明らかになりました。
この結果を受けて、教育の現場では、文章を正確に把握するために必要な語彙や情報の扱い方の定着など、「読解力」の育成に力を入れて、取り組むようになっています。
社会で重要な役割を担いつつあるAI(人工知能)。子どもたちが社会に出る頃には、今ある職業のいくつかは、AIが行うようになるだろうとも言われています。
しかし、めざましい進化を遂げていくなかで、AIの弱点もわかってきました。そのひとつが「読解力」です。AIは膨大な文章データの整理などを行うこともありますが、情報を処理しているだけで、文章を読んで理解しているわけではなく、考えを生み出すことはできません。
けれども、人間は文章を読んで理解した上で、自分自身の考えを深め、意見を述べることができます。そのため、AIが普及しても、「読解力」が高い人材は必要とされると考えられていますよ。
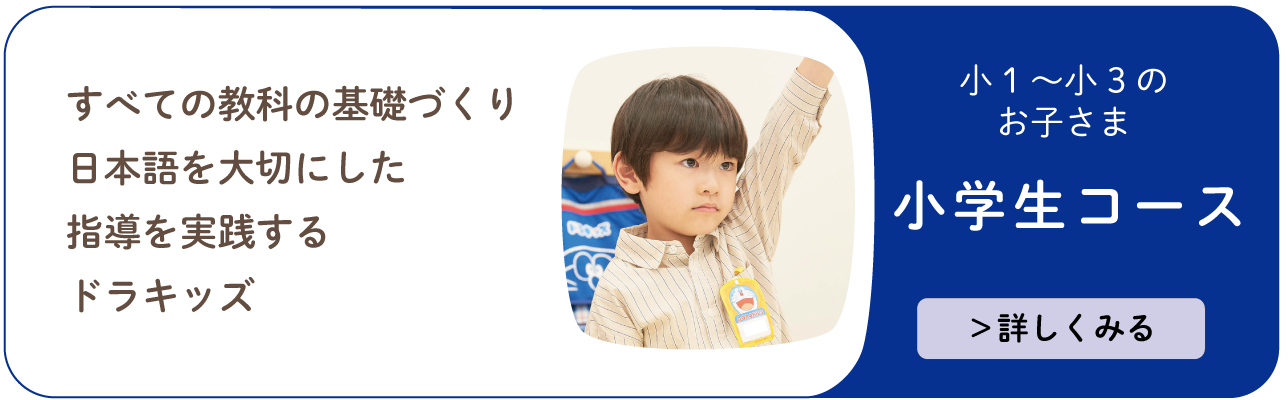
「読解力」はすぐに身に付くものではないと言われていますから、小学生の頃から「読解力」向上を意識した育て方をしておきたいですよね。日常生活での取り組み方法を紹介していきましょう。
●読書を習慣にする
まずは、読むことを習慣にして、文章に親しむようにしましょう。最近は「読解力」向上を狙いとして、小学校の朝学活で10分読書などを設けていますが、ご家庭でも夕食後や就寝前に10分間本を読む時間を作ってみてはいかがでしょうか?
読書を習慣にすると、知らなかった言葉との出会いがもたらされ、語彙力の増加につながります。さまざまな文章に触れることで表現方法にバリエーションがあることを知りますし、新しい知識も増えていきます。登場人物の気持ちを推し量る想像力や自分の考えを深める思考力を高めることにもなるでしょう。
●声に出して読む
本を読む際に声に出して読むこともぜひ行って欲しいことです。目だけで文字を追う黙読では、飛ばし読みがクセづいてしまい、正しい日本語の使い方や文章の成り立ちを身に付けることができなくなってしまいます。保護者の方がお子さまの音読を聞くことで、正しく文章を読んでいるか、確認することもできます。
●読みたい本を読む
本を選ぶ時には、読みたい本をお子さま自身に選ばせてあげましょう。
自分で選ばず、与えられていると、「本を読むのが楽しくない」「文章を見るのが苦痛」と感じてしまうかもしれません。先述のOECD(経済協力開発機構)が実施した国際学習到達度調査の結果を受けて作成した国立教育政策研究所の報告書には、"読書を肯定的に捉える生徒や本を読む頻度が高い生徒の方が「読解力」の得点が高い"と記されています。お子さまが、「文章を読むことって楽しい!」と思えるようにしてくださいね。
また、難しい本を無理して読む必要もないですよ。興味を引かない内容や難しいことが書いてある本を読んでも、字面を追っているだけになってしまう可能性があります。それでは、文章を読んで理解する「読解力」を伸ばすことには結びつきません。お子さま自身が興味を持つ本を読むようにしてくださいね。
●文章で会話をする
親子で会話をすることも「読解力」向上の鍵を握ります。家庭での会話が多いほど、語彙力は伸びると考えられているんですよ。
会話を交わす際には、文章で話すようにしましょう。
例えば、「ごはん。テレビ、消して」と話すのではなく、
「夕食を作ったから、食べようね。テレビのスイッチを消してきて欲しいな」と言うようにしてくださいね。
また、お子さまが順序立てて説明できるように、質問したり、相槌を打ったりするのも良いですよ。
日常的に正しい日本語を使った会話を行っていると、正しい文章で読む・書く力が自然に身に付きます。
●読んだ本について話す
読書をおすすめしましたが、読むだけではなく、本の内容を話すことも習慣にしましょう。「何について書いてある本を読んでいたの?」「読んだ後に、どんなことを感じた?」など問いかけて、お子さまに説明してもらいます。お子さま自身の考えや感情を引き出すように話しかけていきましょう。親子でお互いに読んだ本の内容を説明したり、感想を述べ合ったりすることを楽しむのも良いですね。
ご家庭や学校とは異なる環境で、先生やお友だちと言葉を交わすことは新しい言葉や表現の獲得になると考えられます。
日本語を大切にした指導を実践する『ドラキッズ』の小学生コースでは、国語や算数のテキストを声に出して読むといったように文章を読んで理解することを授業内で取り入れています。
"論理的な言葉"の使い方を習得していく時期であることも踏まえ、読解・作文トレーニングを定期的に実施するなど、「読解力」向上をめざした段階的な取り組みを行っているのが特徴です。
プロ講師が指導するクラスは少人数制で、お子さま一人ひとりの苦手領域の発見と、適切な「読解力」指導を心がけているので、「もっと読解力を伸ばしたい」「さまざまな学びの場で、我が子の可能性を広げたい」と思うなら、ぜひ参加をご検討ください。